カスハラ対応の三つのポイント
近年、理不尽なクレームや度を越した要求、暴言や暴行といった「カスタマーハラスメント」が問題になっています。そうした影響もあって、独立をするとき、お客様からの“カスハラ”を気にする人は多いかもしれません。厚生労働省もカスハラを取り巻く状況を深刻に受け止めており、「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を作成し、カスタマーハラスメントを想定した事前の準備や、実際に起こった際の対応などをまとめた基本的な枠組みを紹介しています。
一方で、2019年6月に改正された「労働施策総合推進法等」を受けて、カスタマーハラスメントの被害を受けたスタッフへの配慮や被害を防止するための取り組みを行うことが必須になりました。企業の大小を問わず、カスタマーハラスメントへの対策を用意しておくことが当たり前の時代になっています。
ただ手探りで対策を進めていくにはあまりにも大きなテーマになってしまうでしょう。今回、三つのポイントを紹介するので、ぜひ自店の取り組みの参考にしてみてください。
クレームとカスハラの違いとは
カスハラは受けた従業員が精神的な苦痛を感じ退職したり、店舗の士気が下がったりするため、お店としては確実に撃退したいでしょう。しかし、正当なクレームは店舗のレベルアップにつながります。できれば真摯に受け止めて、しっかりと対応をしていきたいところです。ただ、クレームとカスハラは、どちらも企業や店舗に何らかの「非」があったり、お客側がそう申し立てたりすることがきっかけになるため、その線引きが非常に難しいです。それでもそこをしっかりと見極めることができないと、会社に大きな損失が発生してしまいます。
クレームは一言でいうと改善へのヒントです。企業によっては、クレームではなく、ご要望やご指摘などの言葉に置き換えているケースもあります。収益の向上につながるため話の腰を折らずに傾聴する姿勢を持つことが重要です。
一方で、カスハラは不当な要求を通すため、執拗に暴言や迷惑行為が続きます。収益を低下させる不当で法外な要求のため、対応すればするほど何らかのロスが必ず発生してしまいます。代表的なロスが「時間的ロス」と「金銭的ロス」「精神的ロス」「人材流出ロス」の四つです。特に人手不足で採用が難しい今、人材流出ロスは企業にとって大きなダメージです。「カスハラに対応したくない」という理由で優秀な人材が抜けてしまうと、店舗のクオリティが下がり、最終的には企業の競争力の低下を招いてしまう危険性はあります。こうした事態を防ぐためにも、まずはクレームとカスハラを見極め、カスハラに対して毅然とした対応を取っていきましょう。
お客様の話を四つに分類しよう
クレームとカスハラを見極める際、お客様の話を「事実」「不満」「意見」「要求」の四つに分類しましょう。それぞれ対応の方向性があり、一つ一つ丁寧に潰していかないといけません。それがカスハラ対応の三つのポイントの一つ目にもなります。
まず「事実」と「不満」です。事実は、しっかりと掘り下げていきましょう。不満は顧客満足度の向上に欠かせません。いわば、ご要望やご指摘などの言葉に置き換えることができます。すぐに潰して、店舗のクオリティを上げていってください。
意見の対応は「傾聴」「感謝」「謝罪」「検討」の四つに分かれます。賛同できない自説を繰り返す人もいますが、否定をせずに「さようでございますか」などの表現にとどめて対応をしていってください。
最後の要求は、お店の対応を一本化して一貫した対応をしましょう。対応がぶれてしまうと、付け入る隙を与えてしまい、事態が収束できなくなってしまいます。肝になるのが意見と要求が一緒になった状況への対応です。ここの対応を間違えると、カスハラに屈することになるので注意をしなければなりません。
初期対応の基本を徹底しよう
カスハラ対応の三つのポイントの二つ目は、適切な初期対応を押さえることです。初期対応は慎重かつ冷静に行う必要があります。それを実現する上で重要なのが「話を聞くに徹する」「事実関係の確認・明確化」「対応時の内容の記録・共有」の三つです。
「話を聞くに徹する」とき、お客様の会話を「事実」「不満」「意見」「要求」の四つに分類することを心がけましょう。それだけで事態が整理されて、対応すべきポイントが一気に明確になります。ここで特に重要なのが「事実」です。
だからこそ「事実関係の確認・明確化」もとても大切なフェーズになります。ここを誤ると状況判断がうまくいかず、カスハラに屈してしまうことになりかねません。事実確認で押さえておくのは「When・Where・Who・What・Why・How・How Many・How Much」の5W3Hです。ここを徹底して、事実を掘り下げていくだけでもカスハラに負けるリスクを格段に減らすことができます。
「対応時の内容の記録・共有」で欠かせないのがメモです。メモを取ると、話が可視化され、論点のすり替えや話題転換にもスムーズに対応できます。またメモを使って復習することで相手の一方的なペースに巻きこまれず、上手に間をとって対応ができるなどメリットは非常に多いです。

お店の方向性を明確に打ち出そう
カスハラ対応の三つのポイントの三つ目は、会社の方針をあらかじめ決めておくことです。理不尽なクレームや度を越した要求が起こった際、会社としての方向性が定まっていないと謝るべきではない場面でスタッフが謝ってしまい、問題がさらに複雑になる可能性があります。現場に柔軟な対応を求めても、普段から「お客様第一」を会社から教えられていたら、例え理不尽な要求であっても自主的な判断で毅然とした対応ができません。だからこそ、カスハラに対しては「スタッフを守る」というメッセージをお店が発信し、対応の方向性を決めておくことが必要です。そうするとカスハラを行う人から暴言や暴行、威圧行為を受けたり、誹謗中傷や罵詈雑言が続いたりしたときも「それ以上は止めてください」と、毅然とした対応を取ることができます。
こうした意思表示をしたにもかかわらずカスハラが続くようなら「拒絶の意思表示をしたのにカスハラを行う人が自らの判断で続けた」という既成事実をつくり出せ、行為の違法性を明確にできます。例えるなら、イエローカードで牽制し、最後にレッドカードを出すイメージです。不当な要求や理不尽なクレームには的確に対応する。そこにカスハラ撃退のポイントが隠されているともいえるでしょう。
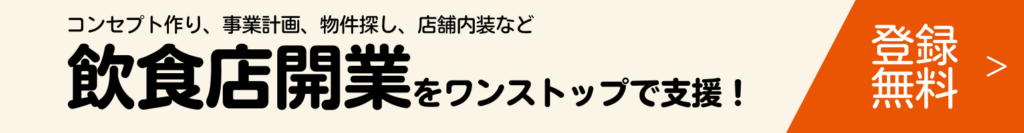
カスハラのロジックを押さえておこう
最後に、カスハラを行う人のロジックも押さえておきましょう。彼らには自分の考えや気持ちといった意見を認めさせて、不当で過剰な要求を通そうとする共通点があります。つまり、謝罪させて自分の要求を受け入れざるを得ない心理的状況に追い込むのが、彼らのロジックなのです。だからこそ、考え・気持ちと、要求を切り離して対応しなければなりません。大切なのは考えや気持ちは受け入れても、要求には応じないようにすることです。
カスハラの対応では一般論や正論を振りかざされて同意を求められたり、些細なことで謝罪を要求されたりします。謝罪すべきところは謝罪をしますが、「だったら〇〇しろよ」といった不当な要求が飛び出したら、そこはキッパリと断らないといけません。要求が通らないと「さっき謝っただろう」とか「悪いと思っているんだろう」といった言葉で返されますが、決して屈しないでください。「ご意見として承る」とか「ご期待に添えず申し訳ない」といった対応をし、相手の打ち手をなくしていきましょう。













