地産地消が飲食店の集客につながる?地産地消のメリットとデメリットについて
近年の飲食業界では、以前にも増して地産地消が注目されるようになりました。本記事では、地産地消が注目される理由と、飲食店が地産地消を取り入れるメリットやデメリットについてご紹介していきます。
飲食店を開業予定の方、地産地消に関心のある事業主の方はぜひ、本記事を参考にしてみてください。
地産地消の意義や取り組み
飲食業界ではなぜ、地産地消が注目を集めているのでしょうか。地産地消とは何か、SDGsとの関連性や取り組みについて解説しています。
地産地消とは
地産地消は、地域で生産したものをその地域で消費することを意味する言葉です。主に農産物や海産物について使われる言葉で、1981年に、当時の農林水産省が食の安全などをアピールするために使用したことがきっかけで広まった概念です。
地産地消に取り組むことで、地域経済の活性化や食文化を守ることにつながります。さらに近年では、持続可能な社会の実現や環境への配慮から、より一層の注目を集めている概念です。飲食業界においては、商品の差別化やブランディングの観点からも、地産地消に取り組む店舗が増えています。
SDGsとの関連性
地産地消は、SDGs目標の達成に関わる取り組みとしても注目されています。たとえば、環境への負担を軽減することや、食品ロス削減などです。
2022年の農林水産省のデータによると、日本の食料自給率は38%と低く、多くの食料を輸入に頼っています。輸入するということは、外国から日本へ、日本到着後は地方へ、と輸送に大量のエネルギーを消費します。食料の輸送量と輸送距離を掛け合わせた数値をフードマイレージと呼びますが、日本はこのフードマイレージが他国よりも高い状況なのです。
地域で生産した食料を地域で消費すれば、フードマイレージを減らすことができ、運搬にかかるコストとCO2の削減にもつながります。他には、輸送に必要な梱包資材の削減にもなります。
また、輸送途中で変形や破損してしまった食材は、市場に並ばず破棄されてしまうこともあるのが現状です。輸送距離が短くなれば、破棄される食材を減らすことができ、食品ロス削減にもつながるのです。
地産地消の取り組み
政府は、以前より地産地消の活動を推奨しており、各地方自治体でも、地産地消の活動支援に取り組む動きが広まっています。学校給食など、子どもたちの健康への配慮や食育としての観点からも取り入れられています。
また、道の駅や直売所での販売や、観光資源として用いられるなどしています。これらの取り組みのうちのひとつとして、飲食業界でも地産地消への取り組みが広がっています。
飲食店が地産地消に取り組むメリット
地産地消に取り組むことによって、飲食店にはどのようなメリットがあるのでしょうか。順に詳しくみていきましょう。
イメージアップと集客につながる
飲食業界の変化や競争は目まぐるしく、消費者の嗜好やトレンドに合わせて変化していく必要があります。ですので、社会全体の健康意識や環境への配慮の高まりに対応していくことが重要です。
地産地消へ取り組むことで、お店のイメージアップや集客につながる効果が期待できます。地産地消の取り組みは、食文化や食の安全に対するお店の理念を表現することでもあり、それがお客様の共感や信頼獲得にもつながります。
また、輸送や流通に向かない食材や、地元でしか採れない希少野菜などを料理に使用することで、他との差別化やブランディングにもなります。
加えて、地元の伝統料理を提供することや、食文化を発信することが付加価値となり、地元のお客様の共感を集めるほか、観光客の集客の効果も期待できるでしょう。
安全で新鮮な食材が手に入る
食材は料理の品質に直接影響するため、飲食店にとって食材の安全性や新鮮さは非常に重要です。
地元の生産者から直接仕入れれば、食の安全性と鮮度を確保しやすくなるのはメリットです。生産者と直接コミュニケーションをとれるため、どのような場所でどのような生産過程をとったかを把握しやすくなります。
また、お店から近い地域で収穫された農産物が手に入るため、輸送に時間をとられない分、鮮度が保たれます。新鮮な食材は、それだけ味も栄養価も高く、顧客満足度の向上にもつながるでしょう。
地域経済の活性化
飲食店が地産地消に取り組むことで、地域経済の活性化や地域社会とのつながりなど社会的価値が生まれることもメリットです。
地域の農産物の需要が増えれば、新たな雇用もうまれ、地域経済が活性化します。
加えて、生産者にとっては、消費者との距離が近くなり、要望や品質向上のための情報収集の機会が増えます。他には、飲食店で地元の食材を使うことによって、食文化を次の世代に継承するきっかけになり、食文化を守ることにもつながります。

飲食店が地産地消に取り組むデメリット
飲食店が地産地消に取り組むことはメリットだけではありません。次に、地産地消に取り組む際の、デメリットについても把握しておきましょう。
食材の種類が限られる
気候や土壌などにより、地域によって育つ食材には限りがあります。そのため、地域で収穫できる食材だけでは、どうしても仕入れる食材の種類が限られてしまいます。
それに、食材によっては、地元産の食材がいちばんよいとは限らないケースもあります。輸送コストを考慮しても、地域外から仕入れる食材の方が品質やコスト面で優れていることもあるでしょう。
全ての食材を地産地消にこだわると、料理の品質を保てないこともあります。経営するうえでは、地産地消に取り組みながらも、柔軟に対応することが必要です。
安定供給の難しさ
地産地消は、食材の安定供給の難しさがデメリットといえます。
農作物は気象条件に大きく影響を受けます。同じ地域内では、同じ気象条件に影響されますので、地域で悪天候や天災、災害などがあると、地元からの食料の仕入れにも影響します。
食材を安定的に仕入れられなければ、お客様に安定して商品を提供できません。特に、人気メニューや定番メニューの食材の仕入れがストップすると、お店の売上にもダメージを受けます。万が一に備えて、他の仕入れ先を確保しておくことや、季節の旬の食材を使ったメニューを充実させるなどの工夫が必要になるでしょう。
価格が高くなりやすい
道の駅や直売所などで販売されている食材は、新鮮な食材がお得な価格で手に入るイメージもあるでしょう。それは、輸送コストや中間マージンが省けるためですが、これはすべてのケースに当てはまるわけではありません。
地元の個人農家は、大量生産をしていない分、価格は高くなる傾向にあります。食材によっては、大量生産した輸入食材の方が安価になりやすいこともありますので、その点にも注意が必要です。
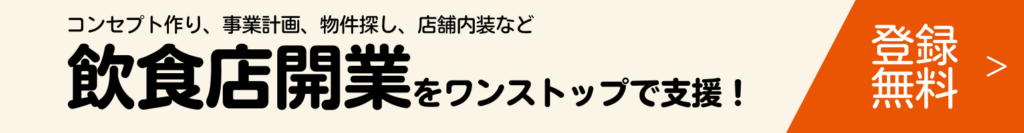
地産地消の取り入れ方
地産地消に取り組むには、まず仕入れ先の開拓と生産者との信頼関係の構築が必要です。自治体によっては、生産者と飲食店のマッチング機会を提供しているところもあるので、これを利用するとよいでしょう。
そして、地元の食材を商品に取り入れるだけでは、それが消費者に伝わりません。
飲食店が地産地消によるメリットを享受するには、その取り組みをPRすることも重要です。自店の取り組みや生産者の情報、生産工程など、SNSやホームページを利用して公開していくなどの工夫が必要です。
まとめ:地産地消のメリットと課題
今回は、地産地消が注目される背景や、飲食店が地産地消を取り入れるメリットおよびデメリットについて解説しました。
地産地消に取り組むことで、ブランディングにつながるだけでなく、環境負担の削減や地域経済への貢献など社会的価値をうみだすことができます。
一方で、食材のバリエーションや安定供給など課題があることも事実です。メリットとデメリットを把握したうえで、自店に合わせた取り組みをしましょう。













